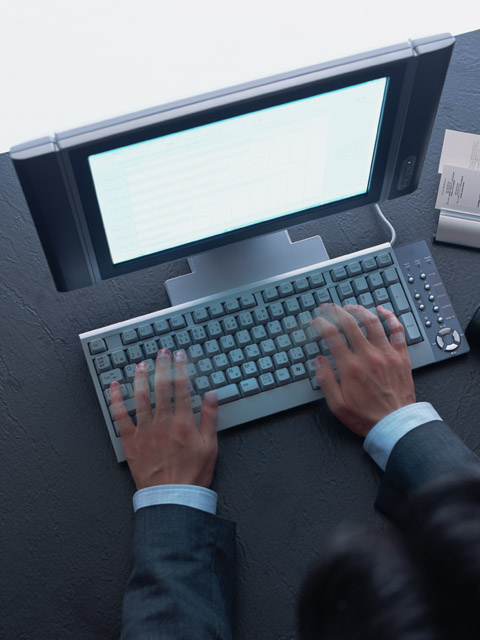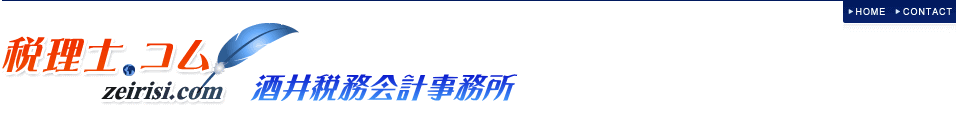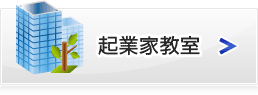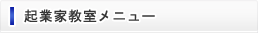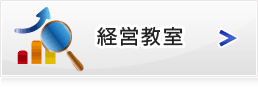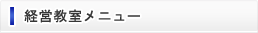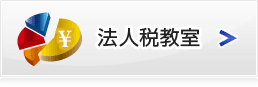試算表の仕組みと損益計算書・貸借対照表の構成
(1)試算表
試算表とは、日々の取引記録の残高を、科目ごとに一定のルールに従って集計した表です。試算表は表中の借方合計(左側)と貸方合計(右側)が一致することによって、取引記録の正確性を確認(試算)することができます。
試算表を分解すると貸借対照表と損益計算書に分解することができます。
なお、利益の計算は、一定期間内の純資産の増加額から計算することもできますし、一定期間の収益の合計金額から費用の合計金額を控除した差額からも計算することもできます。
(2)貸借対照表
貸借対照表(B/S= Balance Sheet)は会社の決算期末時点の財政状態をあらわす計算書です。
簡単に言いますと、決算期末時点にどれだけ財産があって、どれだけ借金があるかをあらわす表です。
貸借対照表は、左側に資金の運用形態である資産、右側にその調達源泉である負債と資本が記載されています。
なお、資産というのは具体的な物や権利のことを指します。
企業は、さまざまな物や権利に資金を投下しますが、これらを取得するには、その元手となる資金を調達しなければなりません。
調達源泉の一つは、銀行等の金融機関からの借入金であったり、仕入先に対する買掛金といった負債です。
もう一つの調達源泉は、株主が出資した資本金や過去の利益の蓄積である利益準備金や剰余金である資本です。
つまり、資産は必ず負債または資本から資金を調達することになりますので、「資産=負債+資本」という関係になり、貸借対照表の左右合計額は必ず一致することになります。
貸借対照表の勘定科目は、一定のルールに従って分類されています。
借方の資産の並び順は、基本的には、上から順番に換金の可能性の高い順に配列されています。
1.流動資産
流動資産とは、1年以内に現金化されるものや「仕入→販売→回収」といった営業循環の流れに乗っている債権等を言います。従って現金預金、売掛金、受取手形の他に、在庫品等も近い将来に換金することを前提としているため、流動資産に分類されます。
なお、流動資産の中でも、特に換金性の高い資産である現金預金、受取手形、売掛金、有価証券を指して当座資産と区分する場合もあります。
2.固定資産
固定資産は建物や土地といった有形固定資産と電話加入権や借地権といった無形固定資産、投資有価証券や長期貸付金といった投資等の3つに分類されます。なお、貸借対照表は取得原価主義を採用しているため、土地や投資有価証券等に含み益や含み損が含まれていても、取得価額で表示されていますので注意が必要です。
3.繰延資産
繰延資産は開発費や、創立費、賃借建物を借りる再に支払った保証金など、将来にわたって支出の効果が現れる費用の繰延額です。4.流動負債
負債の部の流動負債も、流動資産と同様に、営業循環の流れに乗っているか一年以内に支払い期限のくる負債のことで買掛金や短期借入金等がこれに当たります。5.固定負債
固定負債は一年を超えて支払い期限のくる長期借入金や退職給与引当金等の負債となります。 この流動負債と固定負債を合わせて経営分析では他人資本と呼び、資本の部は、原則として返済期限のない長期に安定した資金の源泉で、自己資本といいます。
さらに他人資本と自己資本を合わせた合計を総資本と呼んでいます。
(3)損益計算書
損益計算書(P/L =Profit and Loss statement)は会社の1年間の経営成績を示す計算書です。簡単に言いますと、「どれだけ収入があって、どれだけ経費がかかった結果、当期の利益(損失)はいくらになりました。」という結果報告書です。
ただし、最終結果の利益だけを見ても、その利益がどのような過程で算出されたのかを知らなければ、その会社の経営状態はどうなっているのか分かりません。
そこで損益計算書は利益の算出過程を分かりやすく表示するように作られています。
損益計算書にはいろいろな利益がでてきますが、その過程を説明しますと、損益計算書は大きく分類すると「経常損益の部」と「特別損益の部」に分かれています。
経常損益の部は、会社が通常の経済活動を行うことにより毎期経常的に発生する損益をまとめたもので、さらにこの中を、会社本来の営業活動による「営業損益の部」と、会社の事業目的外である「営業外損益の部」に区分します。
①売上総利益
営業損益の部の最初にでてくる利益は、売上総利益です。これは本来の会社の活動結果である売上高から、売上原価を控除した「会社の基本となる利益」です。物品販売業でしたら、売却した物品の代金の総額とその物品の仕入に要した代金の総額の差額ということになります。
②営業利益
上記①で算出された売上総利益から、給料、旅費交通費、交際費、水道光熱費、広告宣伝費などの営業活動にかかる費用である販売費や一般管理費を控除した利益が営業利益です。③経常利益
上記②の営業利益に対して、営業外損益の部では、受取利息や配当金など一般の会社にとっては本来の事業目的外(営業外)の収益を加え、さらに支払利息、手形売却損(割引料)などの営業外費用を差し引いて経常利益を計算します。④税引前当期利益・当期利益
特別損益の部には、普段はあまり生じない利益や損失の固定資産売却損益などが計上されます。
経常利益に、特別利益を加え、特別損失を控除すると、その会社の最終利益である税引前当期利益となります。
さらに、この税引前当期利益から法人税等の税金を差し引くと、会社が今期の経営活動であげた成果、いわば手取金額とも言える当期利益が算出されます。
このように損益計算書は、会社の経済活動別に損益を計算し、利益を算出する過程を把握しやすいようになっています。