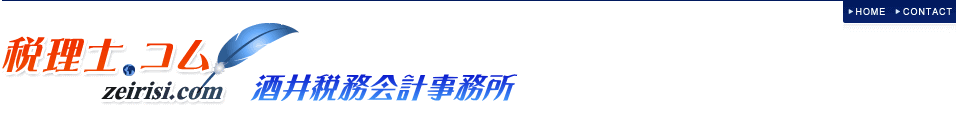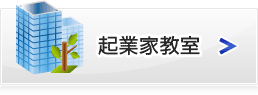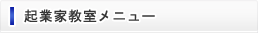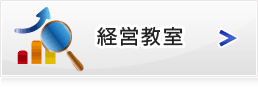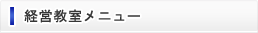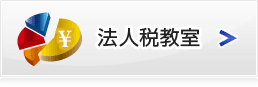毎月の業務の流れ
1.会計資料を頂きます
・現金出納帳等のデータ、領収書、通帳のコピー(写真)などの会計資料をお預かりします。
・毎月月初にデータをメールなどで資料をいただきます。
・データでご用意できない分は、郵送等で頂くことになります。
2.会計ソフトへデータの検証・入力を行います
・自社で入力される方は、入力後のデータの内容確認をさせて頂きます。
・記帳代行を希望される方は、お預かりした資料を元に、データを入力します。
マネーフォワード会計を採用されている場合には、随時データの入力やチェックを行います。
3.月次のお打ち合わせ
完成した会計データを元に作成した、独自の月次の分析表をリアルタイムに報告すると同時に、一緒に経営上の問題点を考えます。
独自の月次の分析表のサンプルはコチラです。
パソコンの操作がわからない時は、リモートコントロールでPCを遠隔操作
→ パソコンの操作が見れて安心です。
※ パソコンの操作が分からない場合や、分析表の説明を行う時などは、リモートコントロールでお客様のパソコンを遠隔操作いたします。
不明な点があればすぐにチャット・メール・電話対応
・来所いただいてもいいですし、ご足労いただかなくても、いつでもチャット、LINE、メール、電話などで気軽にお問い合わせください。・会社や税金のことだけでなく、融資の相談や、経営上のどんなお悩みでも、お気軽にご相談ください!
・試算表などの見方がわからない人にも詳しい説明を行います
→いつの間にか、経理にくわしくなります。
決算業務に関する流れ
1.決算前の検討・対策
決算目前時には、特に注意が必要です。
利益が出ることは大変良いことで、税金を支払った残りの資金を会社に蓄えることにより会社を大きくすることも必要です。
ただし思ったより利益が出てしまい、節税をしたいというような場合には、その対策の提案を行います。
※ オペレーティングリース・短期前払費用の活用・租税特別措置法による優遇措置の検討など
2.決算書の作成
決算整理事項の仕訳処理、決算書の作成、科目内訳明細書の作成、法人事業概況説明書、法人税申告書、消費税の申告書、地方税の申告書等のの書類をお作りし、こちらで各役所へ電子申告等により提出いたします。
各役所の受領印が押された、若しくは電子申告により申告がなされた証明通知付きの申告書や決算書、総勘定元帳などの書類一式をお渡しします。
※ 申告書等はデータでもお渡しすることができますので、お客様が必要な時にいつでも印刷することができます。
2.決算後の対策
新しい事業年度のスタート時には、年間の売上目標の設定や役員報酬の決定・見直し等を行います。
役員報酬は、期首から3ヶ月以内に決める必要があります。途中でむやみに変更はできませんが、適正額であれば全額損金となる役員報酬は節税の最重要項目です。
その他の流れ
源泉所得税の計算・納付
● 源泉所得税の計算・納付
常時従業員数が10名未満の会社で納期の特例を選択している場合には、、毎年7月と1月に、役員報酬や従業員の給料、税理士等の報酬等に係る「源泉所得税」を計算して納付することになります。
※ 通常は役員報酬・給与・報酬を支払った翌月10日に「源泉所得税」を計算して納付することになります。
その他
●年末調整
生命保険料、介護保険料、地震保険料等の控除証明書や住宅取得控除等の資料をお預かりし、役員や従業員の1年間の所得税の最終計算を行います。
「扶養控除等申告書」・「保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」の作成も必要となります。
その後、各人の所得税の還付額や不足額を計算し、源泉徴収簿、源泉徴収票等を作成します。
●法定調書の提出
法人や個人事業主は、法定調書を作成し、1月31日までに役員や従業員に支払った給与や、税理士等に支払った報酬、事務所の家賃や駐車場のい地代等の内容を集計して、税務署に提出する必要があります。
●給与支払報告書
給与を支払う法人や個人事業主は、1月31日まで市区役所へ、市民税の計算の元となる給与支払報告書の作成・提出が必要となります。
この際には個人各人が納付する普通徴収か給与から天引きを行う特別徴収を選択する必要があります。
************************
今なら無料でお試し経営診断をいたします。
・あなたの会社の格付表(銀行があなたの会社をどう見ているかがわかります)
・財務分析表(グラフでわかるので一目瞭然。)
私たちが提供することができるサービス
税務経営の相談や確定申告はもちろんの事、相続税のシミュレーションや、何十社もの保険会社から、どこが一番安いかなどを調べたり、ビルや家を建てる際に複数のゼネコンから見積もりをり、一級建築士にアドバイスをしてもらったり....
→その他の私たちの提供できるサービスを見てみる
問合せへ
-HOME-